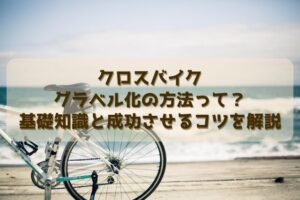愛用のクロスバイクに乗り慣れてくると、「もっと速く、もっと遠くへ…」という思いから、ロードバイクのようなドロップハンドルに憧れを抱く方も多いのではないでしょうか。
しかし、実際にカスタムを考え始めると、ドロップハンドル化する際の費用相場など金銭的な疑問から、ドロップハンドル化するメリットデメリット、そして失敗しないためのクロスバイクをドロップハンドル化する注意点など、知りたいことが次々と出てきます。
この記事では、あなたのそんな疑問に全てお答えします。クロスバイクのドロップハンドル化に必要なものリストはもちろん、ブレーキはそのままでドロップハンドル化するポイントや、ドロップハンドル化でディスクブレーキにする方法といった技術的な詳細まで深掘りして解説。
さらには、具体的なクロスバイクをドロップハンドル化するやり方、クロスバイクのドロップハンドルでおすすめの商品、そしてプロに任せたい場合におすすめの店舗まで、必要な情報を凝縮しました。
 楓
楓本記事が、あなたの理想のバイクライフを実現するための一助となれば幸いです。
【記事のポイント】
1.ドロップハンドル化にかかる、費用の総額と内訳
2.カスタムに必要なパーツと、具体的な交換手順
3.ドロップハンドル化の、メリットデメリットと注意点
4.おすすめのパーツや、カスタムを依頼できる店舗
クロスバイクドロップハンドル化の費用と基本知識


- ドロップハンドル化する際の費用相場って?
- ドロップハンドル化するメリットデメリット
- クロスバイクをドロップハンドル化する注意点
- クロスバイクのドロップハンドル化に必要なもの
- ブレーキはそのままでドロップハンドル化するポイント
ドロップハンドル化する際の費用相場って?


クロスバイクをドロップハンドル化する際の費用は、選ぶパーツのグレードや、作業を自分で行うか専門店に依頼するかによって大きく変動しますが、一般的には30,000円〜50,000円程度が一つの目安になります。もちろん、これはあくまで概算であり、高性能なパーツを選べばさらに高額になる可能性もあります。
| 費用の項目 | 費用の目安(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| パーツ代合計 | ¥20,000~ | STIレバー、ハンドル、ブレーキ、ワイヤー、バーテープなど |
| 工賃 | ¥10,000~¥20,000 | 店舗や作業内容により変動 |
| 総額(目安) | ¥30,000~¥50,000 | 自分で作業する場合は工賃不要 |
この費用の内訳は、主にパーツ代と工賃の二つに分けられます。パーツ代だけでも、ハンドルバー、STIレバー(ブレーキと変速機が一体化したレバー)、ワイヤー類、バーテープなど、交換が必要な部品は多岐にわたります。
これらを新品で揃える場合、エントリーグレードのものでもおおよそ20,000円〜30,000万円程度は、必要になると考えておくとよいでしょう。
一方、作業を自転車専門店に依頼する場合、上記のパーツ代に加えて工賃が発生します。工賃は店舗や作業の複雑さによって異なりますが、10,000円〜20,000程度が相場です。
安全に関わるブレーキや変速機の調整を含む大掛かりなカスタムのため、専門的な知識と技術を持つプロに任せるのが安心です。



ドロップハンドル化は、新しいロードバイクを購入するよりは安価に実現できる可能性がありますが、決して安価なカスタムではないことを理解しておくことが大切です。
ドロップハンドル化するメリットデメリット


クロスバイクのドロップハンドル化には、魅力的なメリットがある一方で、理解しておくべきデメリットも存在します。カスタムを検討する際は、両方の側面を把握しておくことが後悔しないための鍵となります。
メリット
1.多様な乗車姿勢がとれる
ドロップハンドルの最大の利点は、握る場所を変えることで複数の乗車姿勢をとれる点です。上部のフラット部分、ブレーキレバー部分(ブラケット)、下部のカーブ部分(下ハンドル)を使い分けることで、長距離を走る際の体の負担を分散させ、疲労を軽減できます。
2.空気抵抗の削減
ブラケットや下ハンドルを握ることで、フラットハンドルよりも深い前傾姿勢をとれます。これにより、走行中の空気抵抗が減り、特に平坦な道や向かい風の中での巡航速度を維持しやすくなるでしょう。
3.スポーティーな外観
ロードバイクの象徴ともいえるドロップハンドルは、見た目をより本格的でスポーティーな印象に変えてくれます。愛車への愛着がさらに深まるという点も、大きなメリットと考えられます。
デメリット
1.本格的なロードバイクにはならない
ハンドルを交換しても、クロスバイクが完全にロードバイクになるわけではありません。フレームの設計思想(ジオメトリー)が異なり、特にトップチューブが長めに設計されているクロスバイクでは、ハンドル位置が遠くなりすぎてしまい、最適なポジションが出せない場合があります。
2.ブレーキの感覚が変わる
クロスバイクに多いVブレーキから、STIレバーで操作可能なブレーキ(ミニVブレーキなど)に変更すると、ブレーキの制動力や操作感が変わることがあります。フラットハンドル用のレバーに比べて、力が伝わりにくいと感じる可能性も否定できません。
3.追加の費用がかかる
前述の通り、ハンドル交換には多くの関連パーツの購入費用と、場合によっては専門店の工賃が必要です。



もう少し予算を追加すれば、エントリークラスのロードバイクが購入できてしまうケースもあるため、費用対効果を慎重に検討する必要があります。
クロスバイクをドロップハンドル化する注意点


クロスバイクのドロップハンドル化を成功させるためには、いくつかの重要な注意点を事前に理解しておくことが不可欠です。見た目の変化だけに目を奪われず、安全性や互換性の問題をクリアしなければ、快適なサイクリングは望めません。
フレームジオメトリーの違いを理解する
クロスバイクとロードバイクでは、フレームの設計が根本的に異なります。特に注意すべきは「トップチューブ長」です。一般的にクロスバイクは、状態を起こした楽な姿勢で乗れるようにトップチューブが長めに設計されています。
ここに前方へ伸びるドロップハンドルを装着すると、ハンドルまでの距離が想定以上に遠くなり、無理な前傾姿勢を強いられる可能性があります。
この問題を解決するためには、現在ついているステムよりも短いものに交換したり、ハンドルバーの手前側へのカーブ(リーチ)が短い、「ショートリーチ」タイプのドロップハンドルを選んだりといった、工夫が求められます。
パーツの互換性を必ず確認する
ドロップハンドル化は、単にハンドルを交換するだけの単純な作業ではありません。関連する多くのパーツに互換性の問題が生じます。
1.ブレーキレバーとブレーキ本体
クロスバイクで主流の「Vブレーキ」は、ドロップハンドル用の「STIレバー」ではワイヤーの引き量が合わず、正常に作動しません。多くの場合、STIレバーに対応した「ミニVブレーキ」への交換が必要となります。
2.変速機(ディレイラー)
使用している変速機の段数(リア8速、9速など)と、新しく購入するSTIレバーの段数を合わせる必要があります。特にリア10速以上のコンポーネントでは、マウンテンバイク系とロードバイク系で互換性がない場合があるため、より慎重な確認が大切です。
3.ハンドルとステムのクランプ径
ハンドルをステムに固定する部分の直径(クランプ径)には、「25.4mm」「31.8mm」など複数の規格が存在します。現在使用しているステムを流用する場合は、そのステムに適合するクランプ径のドロップハンドルを選ぶ必要があります。



これらの互換性を無視してパーツを購入してしまうと、取り付けができなかったり、安全に走行できなかったりする事態に陥ります。
クロスバイクのドロップハンドル化に必要なもの


クロスバイクのドロップハンドル化には、ハンドルバー本体以外にも、様々な専用パーツと工具を準備する必要があります。ここでは、カスタムに最低限必要となるアイテムを一覧で紹介します。
必要なパーツ
| パーツ名 | 役割・概要 |
|---|---|
| ドロップハンドル | 肩幅やフレームに合う幅・リーチを選ぶカスタムの主役 |
| STIレバー | ブレーキと変速を一体で操作する専用レバー。段数に合わせて選択 |
| ブレーキ本体 | STIレバーと互換性のあるミニVブレーキへの交換が一般的 |
| ステム | ハンドル位置を調整するパーツ。短いものに交換する場合が多い |
| バーテープ | ハンドルに巻くテープ。滑り止め・衝撃吸収の役割 |
| ワイヤー類 | ブレーキ・シフトワイヤー。長さが変わるため新品交換が推奨 |
必要な工具
| 工具名 | 役割・概要 |
|---|---|
| 六角レンチセット | ステムやブレーキ、レバー類の着脱に必須 |
| ワイヤーカッター | ワイヤーをきれいに切断する専用工具。ニッパーでは代用困難 |
| トルクレンチ | 規定トルクで締め付け、破損や緩みを防ぐ |
| プラスドライバー | 主に変速機の調整で使用 |
これらのパーツや工具は、自転車専門店やオンラインストアで揃えることができます。



特にトルクレンチは、安全な組み立てのためにぜひ用意したいアイテムです。
ブレーキはそのままでドロップハンドル化するポイント


「ブレーキはそのまま使えるの?」という疑問は、ドロップハンドル化を検討する際に多くの方が抱く点です。この問いに対する答えは、多くの場合、ブレーキ本体の交換が必要になるというのが実情です。
その理由は、クロスバイクに標準装備されていることが多いVブレーキと、ドロップハンドルで使用するSTIレバーとの間にある、ワイヤーの「引き量」の違いにあります。
簡単に言うと、STIレバーを引く力でVブレーキを正しく作動させることができないのです。STIレバーでVブレーキを無理に引こうとすると、ワイヤーを引き切れずに十分な制動力が得られないという、非常に危険な状態に陥ります。
この問題を解決するための一般的な方法が、「ミニVブレーキ」への交換です。ミニVブレーキは、Vブレーキの一種でありながら、STIレバーと同じワイヤー引き量で動作するように設計されています。
これにより、ドロップハンドルでも適切なブレーキ性能を確保することが可能になります。
ただし、この組み合わせはメーカーが公式に推奨しているものではない場合もあるため、取り付けや調整は自己責任で行うか、専門知識のあるショップに依頼することが賢明です。
ごく稀なケースとして、お乗りのクロスバイクがロードバイクと同じ「キャリパーブレーキ」を装備している場合は、ブレーキ本体を交換せずに、STIレバーと組み合わせられる可能性があります。



まずはご自身の自転車のブレーキタイプを確認することが、最初のステップと言えるでしょう。
実践的なクロスバイクドロップハンドル化の費用と手順


- クロスバイクをドロップハンドル化するやり方
- ドロップハンドル化でディスクブレーキにする方法
- クロスバイクのドロップハンドルでおすすめの商品
- クロスバイクのドロップハンドル化でおすすめの店舗
- クロスバイクのドロップハンドル化でよくある質問
クロスバイクをドロップハンドル化するやり方


クロスバイクのドロップハンドル化は、複数の工程を含む大掛かりな作業ですが、手順を一つずつ丁寧に進めれば、自分で行うことも可能です。ここでは、大まかな作業の流れを解説します。
まず、現在のハンドル周りのパーツをすべて取り外します。グリップ、ブレーキレバー、シフター、ベルなどを順番に外していきましょう。次に、ステムのボルトを緩めてフラットハンドルバー本体を取り外します。
新しいステムとドロップハンドルを取り付けます。この段階では、ボルトは完全に締めず、後で角度調整ができるように軽く固定しておくのがポイントです。続いて、STIレバーをハンドルに通し、自分が握りやすい位置に仮止めします。
前述の通り、多くはVブレーキからミニVブレーキへの交換が必要です。古いブレーキ本体をフレームから外し、新しいミニVブレーキを取り付けます。その後、STIレバーからブレーキ本体まで、新しいブレーキワイヤー(インナーワイヤーとアウターケーブル)を通します。
ブレーキと同様に、STIレバーから前後の変速機(ディレイラー)まで、新しいシフトワイヤーを通します。ワイヤーを張ったら、変速がスムーズに行えるようにディレイラーの調整を行います。この調整は非常に繊細な作業であり、カスタムの中でも特に難易度が高い部分です。
すべてのワイヤー類の取り回しと調整が完了したら、ハンドルにバーテープを巻き付けます。これが終われば、見た目も一気にロードバイクらしくなります。最後に、実際にまたがってみて、ハンドルの角度やレバーの位置を最終調整し、すべてのボルトをトルクレンチで規定のトルクで締め付けて完成です。



安全に作業を行うため、各工程で少しでも不安を感じたら、無理をせずに専門のショップに相談することをお勧めします。
ドロップハンドル化でディスクブレーキにする方法


近年、クロスバイクでもディスクブレーキ搭載モデルが増えてきました。ディスクブレーキ搭載のクロスバイクをドロップハンドル化する場合、そのブレーキが「機械式」「油圧式」かによって、難易度と方法が大きく異なります。
油圧式ディスクブレーキの場合
油圧式ディスクブレーキを搭載したクロスバイクのドロップハンドル化は、ハードルが非常に高いと言えます。その理由は、互換性のあるパーツの選択肢が極めて限られるためです。油圧ディスクブレーキをドロップハンドルで操作するには、油圧対応のSTIレバーが必要になります。
しかし、クロスバイクに採用されがちな8速や9速といったコンポーネントに対応する油圧STIレバーは、市場にほとんど存在しません。
もしカスタムを行うのであれば、STIレバー、ブレーキキャリパー、そして変速機一式を、互換性のあるロードバイク用コンポーネント(例えばSHIMANOのGRXシリーズなど)に総交換する必要が出てくるでしょう。これは非常に高コストなカスタムとなります。
機械式(ワイヤー式)ディスクブレーキの場合
一方、ブレーキの作動をワイヤーで行う機械式ディスクブレーキの場合は、比較的容易にドロップハンドル化が可能です。機械式ディスクブレーキは、Vブレーキやキャリパーブレーキと同じように、ワイヤーで操作します。ロードバイク用のSTIレバーの中には、機械式ディスクブレーキに対応したモデルも多く存在します。
そのため、STIレバーとブレーキの互換性を確認して適切なモデルを選べば、油圧式ほど複雑な問題を抱えることなく、ドロップハンドル化を実現できます。



もし、ディスクブレーキ搭載のクロスバイクでカスタムを考えているなら、まずはご自身の自転車のブレーキがどちらのタイプかを確認することが重要です。
クロスバイクのドロップハンドルでおすすめの商品


ドロップハンドル化を決めたら、次はいよいよパーツ選びです。特にハンドルの選択は、乗り心地を大きく左右する重要なポイントになります。ここでは、クロスバイクのドロップハンドル化に適したハンドルの選び方と、おすすめの考え方を紹介します。
ハンドル選びのポイント
クロスバイクのドロップハンドル化において最も考慮すべき点は、フレームのトップチューブがロードバイクに比べて長いことです。そのため、何も考えずに一般的なドロップハンドルを選ぶと、ハンドルが遠くなりすぎてしまい、乗りにくいポジションになる可能性があります。
この問題を回避するため、ハンドルバーが手前にどれだけ曲がっているかを示す「リーチ」という値が短い、ショートリーチタイプのハンドルを選ぶのが定石です。リーチが70mm〜80mm程度のものを選ぶと、比較的自然なポジションを出しやすくなります。
また、ハンドルのドロップ幅(上ハンドルと下ハンドルの高さの差)が浅い「コンパクト形状」のハンドルも、姿勢の変化が少なく扱いやすいため、初めてドロップハンドルに触れる方には適しているでしょう。素材は、価格を抑えたいならアルミ製、軽量性や振動吸収性を求めるならカーボン製という選択肢があります。
おすすめの製品の考え方
具体的な商品としては、例えばシマノプロ(SHIMANO PRO)の「LT コンパクト」のような、大手パーツメーカーが製造しているエントリーグレードのアルミ製コンパクトハンドルなどが良い選択肢になります。
これらの製品は、品質が安定しており、比較的手頃な価格で入手できるため、コストを抑えつつ信頼性を確保したい場合に最適です。



特定の高価な製品にこだわるよりも、まずは信頼できるメーカーのショートリーチ・コンパクト形状のハンドルから試してみるのが、失敗の少ない選び方と言えるでしょう。
クロスバイクのドロップハンドル化でおすすめの店舗


クロスバイクのドロップハンドル化は、専門的な知識と技術を要する作業です。特に、ブレーキや変速機の調整は安全性に直結するため、少しでも不安がある場合はプロに任せるのが賢明な判断と言えます。
店舗選びのポイント
カスタムを依頼する店舗を選ぶ際は、いくつかのポイントを確認することが大切です。まず、スポーツバイクの販売や修理、カスタムを専門に扱っている店舗であることが大前提となります。その上で、クロスバイクのドロップハンドル化のような、やや特殊なカスタムの実績が豊富かどうかを確認できると、より安心です。
また、パーツの持ち込みに対応してくれるかどうかも、事前に問い合わせておくと良いでしょう。店舗によっては、その店で購入したパーツでなければ作業を受け付けてくれない場合もあります。
親身に相談に乗ってくれて、こちらの要望を理解した上で最適なパーツ構成を提案してくれる、スタッフがいるお店が理想的です。
具体的な店舗の例
全国に店舗を展開している大手スポーツ自転車専門店の一つに、「ワイズロードオンライン」があります。
このような大手専門店は、取り扱っているパーツの種類が豊富で、様々な車種のカスタム実績も多いため、安心して相談しやすいでしょう。専門知識を持ったスタッフが在籍しており、パーツの互換性に関する的確なアドバイスや、安全な組み立てを期待できます。
こちらの記事「ワイズロードオンラインの評判って?口コミでわかる選ばれる理由とは」も、参考にしてください。
もちろん、お住まいの地域にある、信頼できる個人経営のスポーツバイク専門店に相談するのも良い方法です。



まずは一度店舗に足を運び、ドロップハンドル化を検討している旨を伝えて、その対応や雰囲気を確認してみてはいかがでしょうか。
クロスバイクのドロップハンドル化でよくある質問


クロスバイクのドロップハンドル化を検討する中で、多くの方が抱くであろう共通の疑問について、Q&A形式で回答します。
- ドロップハンドルにすれば、完全にロードバイクと同じになりますか?
-
いいえ、完全には同じになりません。前述の通り、クロスバイクとロードバイクではフレームの設計思想(ジオメトリー)が異なります。ハンドルを交換しても、その乗り味や走行性能は、あくまで「ドロップハンドル仕様のクロスバイク」の範疇に留まります。
より速く、機敏な走行性能を求めるのであれば、最初からロードバイクを購入する方が合理的と言えます。
- カスタム作業は自分でできますか?
-
自転車の分解・組み立てに関する一通りの知識と経験があれば、自分で行うことは可能です。しかし、ハンドル、ステム、ブレーキ、変速機といった、自転車の安全性と操作性の根幹に関わる複数のパーツを同時に扱う、非常に難易度の高い作業です。
少しでも自信がない場合や、専用工具を持っていない場合は、安全のためにもプロのいる専門店に依頼することを強く推奨します。
- 費用を安く抑える方法はありますか?
-
費用を抑える方法として、中古のパーツを活用したり、すべての作業を自分で行って工賃を節約したりすることが考えられます。ただし、中古パーツは状態の見極めが難しく、自分で作業する場合は失敗のリスクや安全性の問題が伴います。
コスト削減を追求するあまり、安全性や快適性が損なわれては本末転倒ですので、慎重な判断が求められます。
- ドロップハンドル風の「バーエンドバー」では代用できませんか?
-
フラットハンドルの端に取り付ける「ドロップエンドバー」や「ブルホーンハンドル」は、手軽に握るポジションを増やせるアイテムです。ドロップハンドルの雰囲気を低コストで試すことができます。
しかし、ブレーキレバーやシフターは元の位置のままなので、緊急時のブレーキ操作が遅れたり、変速がしにくくなったりするデメリットがあります。本格的なドロップハンドルの機能性や安全性とは異なるものであると理解しておく必要があります。



よくあるQ&Aも、参考にしてください。
【総括】クロスバイクドロップハンドル化の費用対効果
この記事では、クロスバイクのドロップハンドル化に関する費用、メリットデメリット、そして具体的な方法について解説してきました。最後に、本記事の要点を箇条書きでまとめます。
- カスタム費用の相場は、パーツ代と工賃を含め30,000円〜50,000円程度
- 高性能なパーツを選べば、費用はさらに高くなる
- 自分で作業すれば、工賃分の費用は抑えられる
- メリットは、多様な乗車姿勢と空気抵抗の削減
- デメリットは、本格的なロードバイクにはならないこと
- フレームジオメトリーの違いから、ハンドルが遠くなりやすい
- 短いステムや、ショートリーチハンドルでの調整が有効
- カスタムには、ハンドル以外の多くのパーツ交換が必要
- STIレバー、ブレーキ、ワイヤー、バーテープなどが必須
- クロスバイクのVブレーキは、STIレバーと互換性がない
- STIレバーで引ける、ミニVブレーキへの交換が一般的
- 油圧ディスクブレーキのドロップハンドル化は、難易度が高い
- カスタム作業は、安全に関わるため専門店への依頼が推奨される
- 信頼できるスポーツバイク専門店に、相談するのが確実
- 愛車を自分仕様にカスタムする楽しみは、大きな価値がある
【参考】
>>クロスバイクにカゴってダサいの?イメージ回避の選び方と実用ガイド
>>クロスバイクグラベル化の方法って?基礎知識と成功させるコツを解説
>>クロスバイクのギアでやってはいけないこと?選び方や調整のコツとは
>>クロスバイクはスピード重視で失敗しない?最適な選び方とカスタム術
>>クロスバイクのチェーンカバー後付けって?選び方やメンテナンス方法
>>クロスバイクのタイヤ寿命って?劣化サインと交換時期や費用を解説
>>クロスバイクのブルホーンはダサい?後悔しないカスタム術を徹底解説
>>クロスバイクでチェーンが外れた時の対処法って?原因と直し方を解説