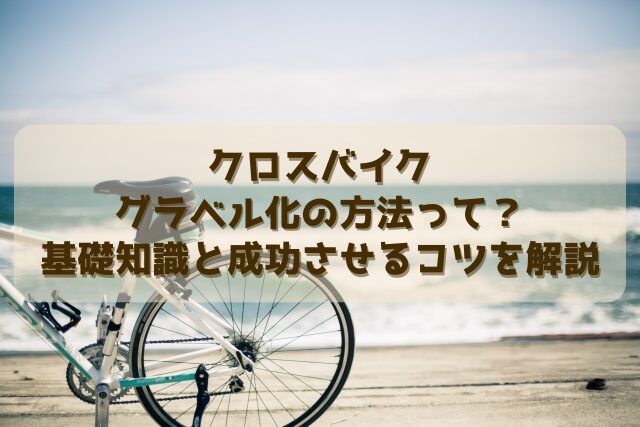近年、街乗りや通勤で使われているクロスバイクに新たな価値を見出す動きとして、クロスバイクのグラベル化が注目を集めています。舗装路だけでなく、未舗装の林道や砂利道をも走れる仕様へとアップデートすることで、走行の自由度が一気に広がるためです。
そもそも、「なぜグラベルクロスが注目されるのか…?」その理由を知れば、グラベル化の魅力がより明確になるでしょう。
この記事では、グラベル化のメリットデメリットや、クロスバイクをグラベル化する方法と必要なパーツ、さらにカスタム前に確認しておくべきポイントまで詳しく解説していきます。
また、パーツ選びに迷いやすいドロップハンドルの選び方や、走行性能を大きく左右するタイヤの選び方についても触れています。もし、既存の完成車ではなく一から自分仕様のバイクを組みたいなら、グラベルバイクを自作する方法にも注目してみてください。
さらに、古いリムブレーキをグラベル化する際の注意点や、グラベルロードに適した装備品といった、実用面での情報も網羅。最後に、これから購入を検討する人に向けて、おすすめのグラベルロードバイクもご紹介しています。
 楓
楓クロスバイクの可能性を広げ、オンロードもオフロードも楽しみたい方にとって、本記事が有益な一歩となるはずです。
【記事のポイント】
1.クロスバイクを、グラベル仕様にカスタムする方法とパーツ
2.グラベル化の、メリットデメリットや注意点
3.タイヤやハンドルなど、装備品の選び方
4.自作や旧型バイクの、グラベル化に関する実践的な知識
クロスバイクをグラベル化する基礎知識


- なぜグラベルクロスが注目されるのか…その理由
- グラベル化のメリットデメリットとは?
- クロスバイクをグラベル化する方法と必要なパーツ
- グラベル化する前にチェックするポイント
- ドロップハンドルの選び方
- グラベルタイヤの選び方
なぜグラベルクロスが注目されるのか…その理由


今、スポーツバイクの世界で「グラベルクロス」が注目されているのは、多用途に使える柔軟性と、気軽にアウトドアライドを楽しめる点にあります。
理由1:幅広く活用できる
グラベルクロスは、舗装された道路だけでなく、未舗装の砂利道や林道のような場所も快適に走行できる設計となっており、通勤・通学から週末のツーリングまで幅広く活用できます。この使い勝手の良さが、多くのサイクリストから支持されている理由の一つです。
理由2:長距離に適している
例えば、一般的なクロスバイクと比較すると、グラベルクロスはディスクブレーキや太めのタイヤを標準装備しており、急な天候変化や路面の悪条件にも対応しやすくなっています。さらに、フレームにはバッグやボトルケージを取り付けるダボ穴が多く設けられており、長距離のアドベンチャーライドにも適しています。
理由3:快適性が高い
また、見た目はロードバイクに似ていますが、乗車姿勢はアップライトで快適性が高く、初めてスポーツバイクに乗る方にも扱いやすいのが特徴です。これにより、「通勤用のバイクが欲しいが、週末はちょっと冒険したい」というユーザー層から高い人気を集めています。
理由4:日常使い&レジャー使いの両立
一方で、ロードバイクやマウンテンバイクと比べると、専門性はやや低めになるため、特定の競技志向が強い方には物足りなさを感じる場合もあります。しかし、日常使いとレジャーの両立を考えたとき、このバランスこそがグラベルクロスの強みとも言えるでしょう。



このように、オンロードもオフロードも楽しみたいというニーズに応えられるのが、グラベルクロスが今注目されている最大の理由です。
グラベル化のメリットデメリットとは?
クロスバイクやロードバイクをグラベル化することで、使い方の幅が広がります。ただし、メリットだけでなく注意すべき点も存在します。ここでは、グラベル化の良い面と悪い面をバランスよく解説します。
メリット
まず大きなメリットは、未舗装路でも安心して走れるようになる点です。太いタイヤやタフなフレーム設計によって、砂利道や林道といったオフロードも安定して走行できます。舗装路しか走れなかったバイクが、一気に行動範囲を広げられるのは非常に魅力的です。
また、グラベル化によって快適性も向上します。タイヤの空気容量が大きくなることで、地面からの衝撃を吸収しやすくなり、長時間のライドでも疲労を感じにくくなります。さらに、バイクパッキングやキャンプツーリングにも対応しやすくなるため、アウトドアの趣味とも相性が良いです。
デメリット
一方で、いくつかのデメリットも無視できません。代表的なのが、重量の増加とスピードの低下です。太いタイヤは重く、舗装路での転がり抵抗が大きくなるため、従来のロードバイクのような軽快な走行感は失われます。
もう一つの注意点は、パーツの交換にかかるコストと作業の複雑さです。ホイールやタイヤだけでなく、ハンドルやブレーキ、コンポーネント全体を見直す必要がある場合もあります。さらに、互換性の確認や調整には専門的な知識が必要であり、初心者にはハードルが高い部分かもしれません。
このように、グラベル化は「どこでも走れる」自由さを得られる反面、「軽さやスピード」というロードバイク本来の性能が落ちるという側面もあります。



用途や目的に合わせて、自分にとって本当に必要なカスタマイズかを見極めることが重要です。
クロスバイクをグラベル化する方法と必要なパーツ


クロスバイクをグラベル化するには、いくつかのパーツを交換・調整する必要があります。ただ、すべての車体で同じ手順になるわけではなく、自転車のスペックや目的によって必要なカスタマイズ内容が変わってきます。
基本的な流れとしては、「ハンドル交換」「タイヤの太幅化」「コンポーネントの互換確認と調整」の、3つが中心になります。
1.ハンドル交換
まずはハンドル。クロスバイクは通常フラットハンドルですが、グラベルバイクではドロップハンドルが主流です。乗車姿勢を前傾にしやすく、長距離向けに適しています。ただし、ハンドルを変えるとシフターやブレーキレバーも対応品が必要になるため、STIレバーに合わせてディレイラーやブレーキの互換性を確認しなければなりません。
2.タイヤの太幅化
次に重要なのがタイヤです。グラベル走行を考えるなら、幅が35mm以上のセミブロックやブロックタイヤに交換するのが一般的です。ただし、太いタイヤを装着できるかどうかはフレームやフォークの「タイヤクリアランス」によって決まります。事前にフレームとタイヤの隙間を測定して、適切なサイズを選びましょう。
3.コンポーネントの互換確認と調整
加えて、ブレーキにも注意が必要です。グラベルでは制動力の高いディスクブレーキが求められますが、取り付け規格が「ポストマウント」「フラットマウント」かによって、選ぶべきキャリパーが異なります。フレームとブレーキキャリパーの規格が一致していないと取り付けができない場合があるので、慎重に確認してください。
さらに、耐久性や泥詰まりに対する対策として、フロントシングルのナローワイドチェーンリングや、チェーン暴れを防ぐクラッチ付きのリアディレイラーに変更するのもおすすめです。
こうしたパーツ選びを適切に行えば、クロスバイクでも十分にグラベルライドを楽しむことができます。



すべてを一度に行うのが難しければ、まずはタイヤから、次にハンドルやブレーキへと段階的に進めるのも現実的な方法です。
グラベル化する前にチェックするポイント
クロスバイクやロードバイクをグラベル仕様に変更する際は、勢いでパーツを揃える前に確認すべきポイントがあります。これを怠ると、せっかく購入したパーツが取り付けられない、思っていた走行ができないといったトラブルに繋がることもあります。
1.タイヤクリアランス
最初に確認すべきなのはタイヤクリアランスです。これは、フレームやフォークとタイヤの間にどれだけ余裕があるかを示すもので、太いタイヤを装着できるかどうかを左右します。例えば、現在700×35Cのタイヤを履いていてフレームとの隙間が1cmあるなら、700×40C程度の太さまでは許容できる可能性があります。
ただし、上下だけでなく左右のクリアランスも、必ず確認してください。
2.ブレーキの取り付け規格
次にチェックすべきはブレーキの取り付け規格です。ディスクブレーキにする場合、ポストマウントかフラットマウントかで対応パーツが異なります。特にフラットマウントのブレーキは、ポストマウント台座には基本的に取り付けできないため、ブレーキキャリパーの選定に注意が必要です。
3.コンポーネントの互換性
また、コンポーネントの互換性も無視できません。特にドロップハンドルに交換する場合、STIレバーとブレーキ・ディレイラーの互換性を調べておかないと、操作ができなくなることもあります。シマノであれば、公式サイトに互換表が掲載されているため、これを参考にすると確実です。
4.ホイールのリム幅と推奨タイヤサイズ
さらに、ホイールのリム幅と推奨タイヤサイズもチェックしておきましょう。現在使っているホイールが細いタイヤ専用であれば、太いグラベルタイヤを装着することで空気圧が不安定になったり、最悪の場合タイヤが外れてしまうこともあります。ホイール側の適正サイズを確認し、タイヤとバランスの取れた選択が必要です。
5.フレームの強度や設計用途
最後に、フレームの強度や設計用途にも目を向けましょう。一部のエントリーモデルのクロスバイクやロードバイクは、舗装路向けの強度設計となっているため、ガレた道や連続する段差を走ると破損リスクが高まります。あくまで「軽めのグラベル走行」で、とどめておく方が無難です。
このように、グラベル化には確認すべき技術的な要素が多く存在します。



事前にチェックポイントを整理しておくことで、無駄な出費やトラブルを防ぎ、安心してカスタマイズを楽しむことができるでしょう。
ドロップハンドルの選び方


グラベル化を検討する中で、ドロップハンドルの導入は大きなステップです。見た目が本格的になるだけでなく、長距離ライドや悪路走行に適したポジションを確保できるため、快適性と操作性の向上につながります。
ハンドル幅
まず注目したいのがハンドル幅です。基本的には肩幅に合わせるのがセオリーとされており、多くの人にとって400mm〜420mmが標準的なサイズになります。ただし、グラベルライドを前提とする場合は、操作安定性を重視してやや広めのハンドル(例:440mm以上)を選ぶ方が、適しています。
特に下り坂や荒れた路面では、広いハンドルのほうが安定感があります。
フレア形状の有無
次に、フレア形状(外側に広がる形)の有無も確認しましょう。グラベルバイク用のドロップハンドルでは、下ハンドル部分が外側に広がる「フレア形状」を採用しているものが一般的です。この形状により、オフロードでのブレーキングやダンシング(立ち漕ぎ)がしやすくなり、腕への負担も軽減されます。
たとえば「Salsa Cowchipper」「Ritchey VentureMax」などが、代表的なフレアタイプのハンドルです。
リーチとドロップの深さ
さらに、リーチとドロップの深さも使い勝手に関係してきます。リーチとはブラケットまでの距離、ドロップは下ハンドルまでの高さを指します。リーチが短くドロップが浅いモデルは、手の移動が少なく、ポジションの切り替えがスムーズになるため、初心者やロングライド志向の方に向いています。
STIレバーとの互換性に注意
一方で、注意しておきたいのがSTIレバーとの互換性です。ドロップハンドルは通常、ブレーキとシフトが一体化したSTIレバーとセットで使う設計になっています。
そのため、クロスバイクに元から付いているフラットバー用のブレーキ・シフターは流用できず、STIレバーに対応するブレーキキャリパーやディレイラーへの、交換が必要になることがあります。
このように、ドロップハンドルの選定は「サイズ」「形状」「互換性」の3点を、バランスよく見極めることが大切です。



見た目や価格だけで選ばず、自分のライドスタイルに最適なモデルを選ぶことで、グラベル化の満足度はぐっと高まります。
グラベルタイヤの選び方
グラベル化を進めるうえで、タイヤ選びはもっとも走行感に直結する重要なポイントです。舗装路と未舗装路を快適に走りたいのか、それとも砂利道メインで走破性を重視したいのかによって、選ぶタイヤの性格が大きく変わってきます。
タイヤクリアランス
まず最初に確認すべきなのがフレームとフォークのタイヤクリアランスです。これは、装着できる最大のタイヤ幅を決める要素で、クリアランスに余裕がないと走行中にフレームと干渉する可能性があります。今装着しているタイヤとフレームの隙間をメジャーで測り、1cm以上の余裕があるかどうかを目安にすると良いでしょう。
タイヤの幅
次に、タイヤの幅を選びます。オンロードとオフロードを半々で走るような使い方であれば、幅は35C〜38Cがバランスの取れた選択です。もし未舗装路が多いなら40C以上のブロックタイヤを選ぶことで、安定性と衝撃吸収性が格段に上がります。一方で、通勤や街乗りが中心なら33C以下の細めのセミスリックタイヤを選ぶと、舗装路でのスピード感が維持しやすくなります。
トレッドパターン
また、トレッドパターン(タイヤ表面の凹凸)も注目したいポイントです。スリックタイプは舗装路向け、セミブロックは万能型、ゴツゴツしたブロックパターンはオフロードに強い傾向があります。自分がよく走る道の種類に応じて、適したパターンを選びましょう。
チューブドorチューブレス対応
さらに、「チューブドorチューブレス」対応の選択も、検討できます。チューブレスタイヤはエアボリュームが確保しやすく、低圧でも走れるため未舗装路に向いています。ただし、タイヤ交換がやや面倒で、専用ホイールが必要になることもあります。日常メンテナンスの手間を減らしたい方には、通常のチューブタイヤが無難です。
使用中のホイールのリム幅
最後に、使用中のホイールのリム幅と選びたいタイヤが適合しているかどうかを確認しましょう。例えば、リム幅が狭いホイールに極太タイヤを装着すると、空気圧が不安定になり、パンクリスクが高まることがあります。
こうした要素を総合的に見ながら選べば、グラベルライドの快適性と安全性が大きく向上します。



迷ったときは、「どこを一番走りたいか」を起点にして、タイヤ選びを進めてみてください。
クロスバイクのグラベル化を成功させるコツ


- グラベルバイクを自作する方法
- 古いリムブレーキをグラベル化する際の注意点
- グラベルロードに適した装備品とは?
- おすすめのグラベルロードバイク
- クロスバイクのグラベル化に関するよくある質問
グラベルバイクを自作する方法


グラベルバイクを自作する場合、完成車を買うよりも自由度が高く、自分の使い方に合った一台を作れるのが魅力です。ただし、パーツの選定や組み立てにはある程度の知識と準備が必要になります。
1.フレーム選び
はじめに取り掛かるのは、フレーム選びです。自作のベースとなるため、ここは最も重要なポイントです。700Cか650Bのホイールが装着できること、ディスクブレーキ台座があること、そして十分なタイヤクリアランスを確保していることがグラベルバイク向きの条件になります。
ダボ穴が多く付いているフレームであれば、キャリアやバッグも取り付けやすくなります。
2.ホイールとタイヤ選び
次に必要なのは、ホイールとタイヤのセットです。グラベルライドでは、エアボリュームのある太めのタイヤが好まれるため、リム幅が広めのホイールを選んでおくと安定感が出ます。チューブレスタイヤを使いたい場合は、ホイールが対応しているかどうかも確認しましょう。
3.ドライブトレイン選び
その後、ドライブトレイン(変速機やクランクなど)を選びます。フロントシングルにするとチェーン落ちが少なく、悪路でも扱いやすくなります。リアディレイラーはクラッチ機構付きのものを選べば、チェーンの暴れを抑える効果があり安心です。シマノのGRXシリーズなど、グラベル専用コンポを取り入れるのも有効です。
4.ブレーキ選び
ブレーキは、安全面で特に重要です。現在の主流は油圧式ディスクブレーキですが、メンテナンスに不安があれば機械式ディスクでも十分な制動力が得られます。ただし、フレームやフォークのブレーキマウント規格(フラットマウントかポストマウント)には注意が必要です。合わないと装着できないため、パーツの互換性確認は必須です。
4.コクピット選び
さらに、「ハンドル・ステム・シートポスト」などの、コックピット周りも使用感に大きく影響します。ドロップハンドルのフレア角やリーチ、シートポストの材質などは乗り心地に直結するため、できれば実際に試乗したり、レビューを参考に選びたいところです。
工具を持っている場合は自分で組み上げることも可能ですが、不安な部分があれば自転車店にパーツ持ち込みで組み立てを依頼するのもおすすめです。費用はかかりますが、安全性と完成度の高さを考えると、初心者には現実的な選択肢です。
このように、グラベルバイクの自作には「パーツ選び・規格の確認・組み立て作業」など多くのステップがありますが、それぞれを丁寧にこなせば、世界に一つだけの理想のバイクが手に入ります。



時間はかかりますが、その過程もまた楽しみのひとつと言えるでしょう。
古いリムブレーキをグラベル化する際の注意点
古いリムブレーキ仕様のロードバイクやクロスバイクをグラベル化する際には、いくつかの技術的・構造的な制約があるため注意が必要です。特にブレーキやタイヤの互換性、車体設計の限界を正しく理解しておかないと、安全性や走行性能に大きな影響を与える可能性があります。
1.タイヤクリアランスの制限
まず最大のポイントはタイヤクリアランスの制限です。リムブレーキバイクはブレーキアーチの構造上、広いタイヤを装着しづらくなっています。特に標準的なキャリパーブレーキでは28Cが限界というケースも多く、35C以上のグラベルタイヤを履かせるのは物理的に不可能なこともあります。
クリアランスを稼ぐために、650Bホイールへの変更を考える方もいますが、リム位置が下がることでブレーキシューが届かなくなり、追加で専用の長いアーチやフォーク交換が必要になる場合もあります。
2.ブレーキ性能の問題
次に注意すべきはブレーキ性能の問題です。未舗装路では急な減速や泥・砂利の影響を受ける場面が多いため、ディスクブレーキのような安定した制動力が求められます。しかし、リムブレーキではホイールが濡れたり汚れたりすることでブレーキの効きが大きく低下します。
この点は安全性に直結するため、グラベル化する場合は特に慎重な判断が求められます。
3.ディスクブレーキ化の可否
また、ディスクブレーキ化の可否についても注意が必要です。古いフレームにはディスクブレーキマウントが付いていないことがほとんどで、後からキャリパーを取り付けるためにはアダプターや専用フォーク、場合によってはフレーム自体の加工が必要になります。
ただし、こうした加工は技術的なハードルが高く、安全性も保証されません。パーツ代に加え、工具や工賃もかかるため、最終的には中古のディスク対応フレームに乗り換えた方がコスト的にも現実的なケースがあります。
4.ホイールの対応問題
さらに、ホイールの対応問題にも目を向ける必要があります。650Bなどに変更する際は、ブレーキ位置だけでなく、ホイールの取り付け方式(クイックリリースかスルーアクスルか)やリム幅が現在の車体に合っているかを確認することが大切です。
ミスマッチがあると、タイヤがはまらなかったり、そもそもホイールが装着できなかったりすることもあります。
このように、古いリムブレーキのバイクをグラベル化するには、想定以上に多くの制約やコストがかかることがあります。軽いグラベルライドを目的とするならば、まずは太めのセミスリックタイヤを履かせて「雰囲気だけ」楽しむ程度に留めるのも一つの選択肢です。



それでも難しい場合は、初めからグラベル対応バイクに乗り換えるという決断も、結果的には賢明な判断と言えるでしょう。
グラベルロードに適した装備品とは?


グラベルロードバイクは舗装路から未舗装の砂利道まで、幅広い路面状況に対応する設計になっています。その特性を活かし、安全かつ快適に走行するためには、装備品の選定が非常に重要です。
単にタイヤやブレーキだけでなく、走行スタイルや目的に応じた補助装備の充実が求められます。
| 装備品 | 内容とポイント |
|---|---|
| パンク修理キット | 予備チューブ、タイヤレバー、携帯ポンプ、CO₂インフレーターなどが必携 |
| 天候やトラブルへの備え | レインジャケット、モバイルバッテリー、充電ケーブルで安心 |
| 積載用のバッグ類 | フレームバッグやサドルバッグで荷物を効率的に収納 |
| 頑丈なケージや工具類 | 緩み防止に丈夫なボトルケージ、マルチツールは現地対応に便利 |
| ライトとベル | 高輝度ライトとベルは安全確保と周囲への配慮に必須 |
1.パンク修理キット
まず最低限揃えておきたいのはパンク修理キットです。グラベルコースでは鋭利な小石や枝が多く、舗装路に比べてパンクのリスクが高くなります。チューブレスタイヤを使用していても、シーラントが間に合わない大きな穴が空くこともあるため、予備チューブやタイヤレバー、携帯ポンプは必携です。
CO₂インフレーターがあると、より素早く空気を入れられるため便利です。
2.天候やトラブルへの備え
次に必要なのが天候やトラブルへの備えです。山間部や林道では急な雨に見舞われることも珍しくありません。軽量なレインジャケットやウインドブレーカーをサドルバッグに常備しておけば、体温低下を防ぎながら走行を続けられます。また、スマートフォンやGPSのバッテリー切れに備えてモバイルバッテリーと充電ケーブルもあると安心です。
3.積載用のバッグ類
長距離やツーリング用途でグラベルを走る場合には、積載用のバッグ類も役立ちます。グラベルバイクの多くはダボ穴が豊富に用意されているため、フレームバッグ、トップチューブバッグ、サドルバッグなどを組み合わせて積載量を増やすことができます。キャンプツーリングを想定するなら、容量50L前後を目安にバッグ類を揃えておくと快適です。
4.頑丈なケージや工具類
また、グラベル特有の悪路ではボトルケージのネジが緩みやすいため、頑丈なケージや工具類も必要になります。マルチツールには「六角レンチ・チェーンカッター・プラスドライバー」が一体になったものを選ぶと、現地でも対応しやすくなります。
5.ライトとベル
安全面で忘れてはならないのがライトとベルです。特にグラベルライドでは、予定より遅れて夕方以降に走行するケースもあり得ます。前後のライトは高輝度でバッテリー持ちの良いモデルを選びましょう。ベルは林道や登山者がいるルートではコミュニケーションの手段としても有効です。
このように、グラベルロードでの走行では「どこを走るか」と同じくらい、「何を持っていくか」が重要です。トラブル時に対応できる装備を揃えておけば、不安なくさまざまな地形を楽しめるようになります。



装備は快適性と安全性を両立させる、もう一つの足とも言える存在です。
こちらの記事「クロスバイクにカゴってダサいの?イメージ回避の選び方と実用ガイド」も、参考にしてください。
おすすめのグラベルロードバイク
グラベルロードバイクを選ぶときは、目的や予算に応じたモデルを選ぶことが大切です。舗装路と未舗装路の両方を走る設計になっているため、安定性や快適性に優れ、ツーリングや通勤にも幅広く対応できるのが特徴です。
ここでは、初心者にも扱いやすく、価格・性能ともにバランスの良いおすすめモデルを紹介します。
| ブランド/シリーズ名 | 特徴 | おすすめポイント |
|---|---|---|
| GIANT Revoltシリーズ | 軽量アルミフレーム、太めのタイヤ | 初めてのグラベルバイクに最適、価格も手頃 |
| FUJI JARIシリーズ | クロモリフレーム、広いタイヤクリアランス | ツーリングやキャンプライドに最適 |
| Cannondale Topstoneシリーズ | アルミフレーム+カーボンフォーク | 快適性と加速性のバランスが優秀 |
| MERIDA SILEXシリーズ | グラベル対応設計、安定性重視 | ロングライド志向におすすめ |
ジャイアント(GIANT)Revoltシリーズ
まず紹介したいのが、「ジャイアント(GIANT)Revoltシリーズ」です。コストパフォーマンスの高さで知られるジャイアントの中でも、Revoltは特にグラベル入門向けに適した1台です。軽量なアルミフレームを採用し、フロントシングルのドライブトレインや太めのタイヤを装備しており、街乗りから林道まで安心して走れます。
価格帯も100,000円~150,000円前後と、比較的手が届きやすいのも魅力です。
FUJI(フジ)JARIシリーズ
次に注目されているのが、「FUJI(フジ)JARIシリーズ」です。もともとツーリングを想定して設計されているため、豊富なダボ穴、広いタイヤクリアランス、荷物を積載しやすいジオメトリーを備えています。クロモリフレームのしなやかな乗り心地も人気の理由で、キャンプツーリングを視野に入れる方におすすめできます。
Cannondale(キャノンデール)Topstoneシリーズ
さらに、「Cannondale(キャノンデール)Topstoneシリーズ」も見逃せません。高剛性で軽量なアルミフレームとカーボンフォークの組み合わせは、舗装路での加速感とグラベルでの快適性を両立しています。一部のモデルには独自のリアサスペンション機構が搭載されており、荒れた路面でもしっかりと衝撃を吸収してくれます。
MERIDA(メリダ)SILEXシリーズ
また、「MERIDA(メリダ)SILEXシリーズ」は、ロードバイク寄りの見た目ながら、グラベル対応に特化した設計になっています。ステアリングが安定しやすく、長距離でも疲れにくいポジションがとれるため、ロングライド志向の方には最適です。ワイドなギア比やディスクブレーキが標準装備されている点も安心材料です。
これらのモデルは、価格、スペック、使いやすさのバランスが取れており、初めてのグラベルバイクとしても十分な性能を備えています。
ただし、購入前には自分の走行スタイルに合ったタイヤ幅やポジションを確かめるためにも、可能であれば試乗してみることをおすすめします。
このように、グラベルロードバイクは選び方次第で街乗りから本格的なアドベンチャーライドまで、カバーできる万能な自転車です。



しっかり比較検討し、自分のライドスタイルにぴったりの1台を見つけてみてください。
クロスバイクのグラベル化に関するよくある質問


クロスバイクをグラベル仕様にカスタマイズしようとする際、多くの人が疑問に感じる点があります。ここでは、初心者がつまずきやすいポイントや、よく寄せられる質問に分かりやすく答えていきます。
- クロスバイクでも本格的なグラベルライドは可能ですか?
-
クロスバイクは元々オンロードと多少のオフロードを両立する設計のため、ある程度の未舗装路は問題なく走行できます。ただし、マウンテンバイクほどの悪路性能は備えていないため、段差や大きな石が多いコースには不向きです。タイヤ幅やブレーキ性能などを調整すれば、林道や砂利道程度であれば十分に楽しめます。
- タイヤだけ変えればグラベル化できますか?
-
タイヤ交換は最も手軽なグラベル化の手段です。現状のフレームとフォークに装着可能な範囲で、太めのセミブロックタイヤやグラベルタイヤを選ぶことで、走行感が大きく変わります。ただし、クリアランスを超えるサイズを無理に装着すると、ブレーキやフレームと干渉する恐れがあるため、必ず事前に測定してから選びましょう。
- フラットハンドルのままでも大丈夫ですか?
-
ドロップハンドルに交換することでポジションの自由度は広がりますが、フラットハンドルのままでも問題なくグラベルライドは可能です。むしろ街乗りとの兼用を考えるなら、取り回しのしやすいフラットハンドルのほうが扱いやすい場面もあります。ブレーキやシフターの互換性も維持しやすく、コストも抑えられます。
- カスタムにどれくらい費用がかかりますか?
-
費用はどのパーツを交換するかによって大きく変わります。タイヤとチューブの交換だけなら10,000円以内で済みますが、ハンドル、ブレーキ、ドライブトレインまで変更するとなると、30,000円〜70,000円以上になることも珍しくありません。特にコンポーネント一式の交換は費用がかさみがちです。
- 自分でパーツ交換するのは難しいですか?
-
タイヤ交換やハンドルの変更程度であれば、初心者でも手順を確認すれば対応可能です。ただし、ブレーキやシフターなどのワイヤー調整、ディスクブレーキの取り付けなどは専門的な知識が必要になる場合があります。作業に不安がある場合は、自転車店に持ち込んで工賃を払って依頼するのが安心です。
- グラベル化したバイクで通勤はできますか?
-
はい、できます。むしろ安定感のある太いタイヤや、雨の日でも安心なディスクブレーキは、通勤バイクとしての信頼性を高めます。ただし、車体がやや重くなること、タイヤの転がり抵抗が増えることでスピードが落ちることは考慮しておくべきです。
このように、クロスバイクのグラベル化は決して難しい作業ではありませんが、知識と準備をしっかりしておくことで、より快適で安全なライドが可能になります。



疑問点を一つずつ解消しながら、自分に合ったカスタマイズを楽しんでください。
クロスバイクグラベル化の基本と実践ポイント総括
記事のポイントを、まとめます。
- グラベルクロスは、オンロード・オフロードの両立が可能
- 太めのタイヤにより、未舗装路での安定性が高まる
- ディスクブレーキで、悪路や雨天時の制動性が向上
- アップライトな乗車姿勢で、初心者にも扱いやすい
- バッグ搭載用のダボ穴が多く、ツーリングにも適する
- タイヤクリアランスの確認は、グラベル化前の必須事項
- フレームによっては、太いタイヤが装着できない場合がある
- ドロップハンドルは、姿勢の自由度と長距離適性が高い
- STIレバー導入時は、互換性のあるパーツ選定が必要
- フレア形状のドロップハンドルは、オフロードで操作しやすい
- コンポーネントの互換性によっては、作業難易度が上がる
- 古いリムブレーキ車は、タイヤ・ブレーキ制限が多い
- タイヤ交換だけでも、手軽なグラベル化は可能
- グラベル装備は、パンク修理キットや積載バッグが必須
- 走行スタイルに合わせたバイク選びが、快適性を左右する
【参考】
>>クロスバイクのギアでやってはいけないこと?選び方や調整のコツとは
>>クロスバイクはスピード重視で失敗しない?最適な選び方とカスタム術
>>クロスバイクのチェーンカバー後付けって?選び方やメンテナンス方法
>>クロスバイクのタイヤ寿命って?劣化サインと交換時期や費用を解説
>>クロスバイクのブルホーンはダサい?後悔しないカスタム術を徹底解説
>>クロスバイクのドロップハンドル化の費用って?方法や注意点を解説
>>クロスバイクでチェーンが外れた時の対処法って?原因と直し方を解説