「折りたたみ自転車は買ってはいけない…」という言葉を目にして、購入をためらってはいませんか。確かに、折りたたみ自転車はその特殊な構造から、一般的な自転車とは異なる側面を持っています。
この記事では、折りたたみ自転車を買ったら後悔するのか、また壊れやすいという噂は本当なのか、といった疑問に答えていきます。折りたたみ自転車のメリットデメリットを客観的に解説し、ママチャリとの比較や通勤で使うのは苦じゃないかという、具体的な悩みにも触れます。
さらに、折りたたみ自転車がおすすめな人とそうでない人の特徴を明らかにし、失敗しないための選び方の注意点とポイントを、詳しくご紹介します。また後半では、具体的なおすすめ人気商品から、注目の電動折りたたみ自転車まで網羅的に解説。
 楓
楓あなたのライフスタイルに、最適な一台を見つけるための、確かな情報が得られるはずです。
【記事のポイント】
1.買ってはいけないと言われる、折りたたみ自転車の具体的な弱点
2.利用シーン別(通勤・街乗り)の、メリットデメリット
3.後悔しないための、選び方のポイントと注意点
4.タイプ別のおすすめ人気商品と、最新の電動モデル
折りたたみ自転車は買ってはいけない…の真相


- 折りたたみ自転車を買ったら後悔する?
- 折りたたみ自転車は壊れやすいって本当?
- 折りたたみ自転車のメリットデメリット
- 折りたたみ自転車とママチャリ…買うならどっち?
- 折りたたみ自転車で通勤するのは苦じゃない?
折りたたみ自転車を買ったら後悔する?


折りたたみ自転車の購入で後悔するケースは、主にその特性を理解せずに選んでしまった場合に起こり得ます。後悔につながる可能性のある主なデメリットは、「走行性能」「価格」に関する点です。
走行性能って?
第一に「走行性能の面」では、一般的な自転車に比べて速度が落ちやすく、不安定に感じることがあります。これは、多くの折りたたみ自転車が採用する小径ホイール(小さいタイヤ)に起因します。
ホイールが小さいと、一度スピードに乗っても慣性が働きにくく、速度が維持しづらくなります。そのため、特に長距離を走ると、速度を保つためにペダルを漕ぎ続ける必要があり、疲れやすさを感じるかもしれません。
また、ホイールが小さいと「フライホイール効果」という、回転による安定性が弱まるため、走行中のふらつきを感じやすくなります。特に乗り慣れていないうちは、この不安定さがストレスになる可能性があります。
価格面はどうなの?
第二に、「価格面」です。折りたたみ自転車は、同じくらいの性能を持つクロスバイクなどと比較して、価格が高くなる傾向があります。折りたたみ機構という特殊な構造や、専用のパーツが必要になるため、製造コストが上がり、販売価格に反映されるからです。
ざっくりとした目安ですが、同等のグレードで1.5倍ほどの価格差が生じることもあります。



これらのデメリットを知らずに、便利そうだからという理由だけで購入すると、「思ったより進まなくて疲れる」「この性能でこの値段は高かった」といった、後悔につながるわけです。
折りたたみ自転車は壊れやすいって本当?


「折りたたみ自転車は壊れやすい…」という懸念は、特に折りたたみ機構という構造的な弱点に由来します。これは、ある意味で事実と言えますが、全てのモデルに当てはまるわけではありません。
壊れやすい主な原因
壊れやすさの主な原因は、フレームの中央やハンドルの根元に設けられた「ヒンジ(関節部分)」です。この部分は、乗車時の体重や走行時の衝撃が集中する、いわば自転車の弱点となり得る箇所です。頻繁に折りたたみを繰り返すことによる金属疲労や、固定が甘い状態での走行は、この部分にダメージを蓄積させます。
具体的なトラブル
具体的なトラブルとしては、走行中の「ギシギシ」という異音の発生が挙げられます。これは、折りたたみ部分のパーツの緩みや摩耗が原因であることが多いです。また、最悪の場合、長年の使用で蓄積したダメージにより、フレームの折りたたみ部分が破損するリスクもゼロではありません。
安価なモデルは要注意
特に注意が必要なのは、10,000円台などで販売されている「極端に安価なモデル」です。これらの自転車は、コストを抑えるために折りたたみ機構の強度や精度が不十分な場合が多く、トラブルが発生する可能性が相対的に高くなります。急にロックが外れたり、ペダルが抜けたりといった、安全に直結する深刻な問題が報告されることもあります。
一方で、信頼できる専門メーカーが製造する高品質なモデルは、開発段階で十分な強度計算と耐久テストが行われています。そのため、適切なメンテナンスをしていれば、簡単に壊れることはありません。



つまり、壊れやすいかどうかは、製品の品質と価格に大きく左右されるのです。
折りたたみ自転車のメリットデメリット


折りたたみ自転車の購入を検討する際には、メリットデメリットを天秤にかけることが大切です。どんな自転車にも長所と短所があり、自分の使い方に合うかどうかを見極めるのが鍵となります。
| 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 保管・携帯性 | 室内保管可・盗難や劣化に強い・車載や輪行で行動範囲拡大 | – |
| 走行性能 | 漕ぎ出しが軽く加速力が高い・街乗りに強い | 速度維持が難しく長距離で疲れやすい・安定性が低い |
| 構造 | – | 折りたたみ機構の異音・破損リスク |
| 価格 | – | 特殊構造で一般的な自転車より高価 |
メリット:コンパクトさと機動力が最大の魅力
折りたたみ自転車の最大のメリットは、やはりその「コンパクトさ」「携帯性」にあります。
1.省スペースでの保管が可能
自宅の玄関やクローゼット、オフィスのデスク下など、駐輪場がない場所でも保管できます。これにより、雨風による劣化や盗難のリスクを大幅に軽減できるのは大きな利点です。
2.持ち運びが容易
軽量なモデルを選べば、電車やバスなどの公共交通機関に持ち込む「輪行」が可能です。また、車に積んで旅先やキャンプ場で使用するなど、行動範囲を格段に広げることができます。
3.高い加速性能
タイヤが小さく軽い分、漕ぎ出しが非常に軽快です。信号の多い市街地でのストップアンドゴーで、すぐにスピードを回復できるため、街乗りに非常に強いと言えます。
デメリット:走行性能と価格が課題
一方、デメリットも存在します。主に走行性能と価格面での課題が挙げられます。
1.速度維持が難しい
小径ホイールは慣性が効きにくいため、一度出したスピードを維持するのが苦手です。長距離では疲れやすさに繋がることがあります。
2.安定性の低さ
ホイール径が小さいことに加え、ハンドルの可動域が広いため、走行時にややふらつきやすく感じられます。慣れが必要な部分です。
3.価格が高め
前述の通り、特殊な構造とパーツのため、同程度の性能の一般的な自転車に比べて価格が高価になる傾向があります。



これらのメリットとデメリットを比較し、自分のライフスタイルにおいて、デメリットを上回るメリットがあるかどうかを判断することが、後悔しない選択につながります。
折りたたみ自転車とママチャリ…買うならどっち?


折りたたみ自転車とママチャリ(シティサイクル)は、どちらも身近な自転車ですが、その用途は大きく異なります。どちらを選ぶべきかは、あなたの自転車の使い方によって明確に分かれます。
言ってしまえば、日常の「足」としての利便性を最優先するならママチャリ、保管場所や「持ち運び」の柔軟性を重視するなら折りたたみ自転車が適しています。
ママチャリの強み
ママチャリの最大の強みは、その「積載能力と実用性」です。標準装備されている前カゴや後付けのリアキャリアを使えば、スーパーでの買い物や通勤・通学の荷物を楽に運べます。また、泥除けやチェーンケースがフル装備されているため、服装を気にせず気軽に乗れるのも魅力です。
26インチや27インチといった大きなタイヤは走行安定性も高く、多少の荷物を積んでもふらつきにくいです。
折りたたみ自転車の強み
一方、折りたたみ自転車の強みは、ママチャリにはない「携帯性と収納性」です。駐輪スペースがない都市部のマンションに住んでいる場合や、自転車を盗難から守るために室内保管したい場合には、唯一の選択肢となることもあります。
また、車に積んで出かけ、旅先でサイクリングを楽しむといった、趣味としての使い方をしたい場合にも最適です。
これを理解した上で、どちらを選ぶか判断するのが良いでしょう。多くの荷物を運ぶ、毎日のお買い物や近所の移動がメイン、という使い方であればママチャリが便利です。



逆に、荷物はリュックで十分、保管場所に制約がある、電車や車と組み合わせて使いたい、というニーズがあるなら、折りたたみ自転車があなたの生活を豊かにしてくれるはずです。
折りたたみ自転車で通勤するのは苦じゃない?


折りたたみ自転車での通勤が苦になるかどうかは、主に「自転車の品質」「通勤距離」「道のりの状況」の3つの要素によって、決まります。一概に苦しいとも快適とも言えず、条件次第というのが実情です。
自転車の品質が鍵
まず「自転車の品質」が、最も影響します。10,000円台の安価なモデルやシングルギア(変速なし)の自転車で、アップダウンのある道を長距離通勤するのは、体力的にかなり厳しいでしょう。速度が維持しにくく、坂道では大きな負担がかかるため、通勤が苦痛になってしまう可能性が高いです。
しかし、ある程度の価格帯(30,000円~)で、スポーツ走行を意識した多段変速付きのモデルであれば、話は変わります。これらのモデルは軽量でフレーム剛性も高く、一般的なママチャリよりも快適に、かつ速く走れることも少なくありません。
20インチ程度のホイールサイズでも、適切なギア比設定がされていれば、必死に漕がなくてもスムーズに進みます。
通勤距離が目安に
次ぎに「通勤距離」が、一つの目安となります。一般的に、自転車通勤が快適に続けられる距離は片道10km程度までと言われています。折りたたみ自転車の場合も、高品質なモデルであればこの距離は十分に射程圏内です。ただし、これ以上の長距離になると、やはりロードバイクやクロスバイクに比べて疲れやすさを感じるかもしれません。
坂道の有無
最後に、「坂道の有無」です。坂道が多いルートの場合、軽量で変速段数の多いモデルを選ぶことが必須条件となります。最近では、坂道でのアシストが強力な電動アシスト付きの折りたたみ自転車も人気があり、これらを選択すれば坂道の多い通勤路も苦にならなくなるでしょう。



適切なモデルを選び、距離や道のりが常識の範囲内であれば、折りたたみ自転車での通勤は十分に可能であり、むしろ満員電車を避ける快適な移動手段となり得ます。
買ってはいけない折りたたみ自転車を避ける選び方


- 折りたたみ自転車がおすすめな人とそうでない人
- 折りたたみ自転車を選ぶ際の注意点とポイント
- 折りたたみ自転車のおすすめ人気商品
- 電動折りたたみ自転車で注目の商品
- 折りたたみ自転車に関するよくある質問
折りたたみ自転車がおすすめな人とそうでない人


折りたたみ自転車は非常に便利な乗り物ですが、その特性上、全ての人におすすめできるわけではありません。あなたのライフスタイルや自転車に求めるものによって、最適な選択肢になるか、あるいは不向きな選択肢になるかが分かれます。
折りたたみ自転車がおすすめな人
以下のようなニーズを持つ方には、折りたたみ自転車は生活を豊かにする最高のパートナーとなり得ます。
1.家の保管場所に限りがある人
マンションの玄関や室内、ベランダなど、限られたスペースに自転車を置きたい方にとって、コンパクトに収納できる点は最大の魅力です。
2.自転車の盗難が心配な人
高価な自転車を屋外に置くのは不安が伴います。折りたたんで室内保管できれば、盗難のリスクを大幅に減らせます。
3.公共交通機関や車と組み合わせて使いたい人
自宅から最寄り駅まで、駅から会社まで、あるいは旅先に車で持って行って現地でサイクリングを楽しむなど、「移動の手段」として柔軟に使いたい方には最適です。
4.街乗りでの機動性を重視する人
漕ぎ出しの軽さと小回りの良さは、信号や人通りの多い市街地で真価を発揮します。
折りたたみ自転車をおすすめしない人
一方で、以下のような使い方を想定している場合は、他のタイプの自転車を検討した方が満足度は高くなる可能性があります。
1.長距離のサイクリングを楽しみたい人
20km以上の距離を本格的に走りたい場合、ロードバイクやクロスバイクに比べて速度維持が難しく、疲れやすさを感じることがあります。
2.スピード感を最優先する人
最高速度自体は大きく変わりませんが、巡航速度(楽に維持できる速度)では、ホイール径の大きい自転車に分があります。
3.多くの荷物を積んで移動したい人
多くのモデルはカゴが付いておらず、積載性を重視した設計にはなっていません。通勤や買い物で常に多くの荷物を運ぶ場合は、ママチャリの方が便利です。
4.自転車のメンテナンスを全くしたくない人
折りたたみ機構という点検箇所が一つ増えるため、一般的な自転車以上に定期的なチェックが望ましいです。



ご自身がどちらに当てはまるか理解できれば、折りたたみ自転車の必要性も見えてきます。
折りたたみ自転車を選ぶ際の注意点とポイント


後悔しない折りたたみ自転車を選ぶためには、いくつかの重要なポイントと注意点を押さえておく必要があります。価格やデザインだけで選んでしまうと、安全性や使い勝手の面で失敗しかねません。
買ってはいけない激安品を避ける
まず最も大切なのは、10,000円台などで売られている極端に安価なモデルを避けることです。これらの製品は、安全性を担保するためのコストが削られている可能性が高いです。フレームの剛性不足や、ブレーキ・変速機の精度の低さ、折りたたみ部分の強度の弱さなど、多くのリスクを抱えています。
信頼できるメーカーの製品でも、最低30,000円前後からの価格帯を目安にすると良いでしょう。
用途に合わせた「タイヤサイズ」と「重量」を選ぶ
折りたたみ自転車の使い勝手は、タイヤサイズと車体重量で大きく変わります。それぞれの特徴を理解し、自分の主な用途に合わせて選ぶことが鍵となります。
| 携帯性重視 | バランス重視 | 走行性重視 | |
|---|---|---|---|
| タイヤサイズ | 14~16インチ | 16~20インチ | 20インチ以上 |
| 特徴 | 非常にコンパクト・安定性低め・段差に弱い | 走行性と携帯性のバランス良い・一般的 | 走行安定・速度維持しやすい・折りたたみ時大きめ |
| おすすめ用途 | 輪行・車載・短距離移動 | 街乗り・時々輪行・オールラウンド | 通勤・長めのサイクリング |
| 超軽量 | 軽量 | 標準 | |
|---|---|---|---|
| 車体重量 | 10kg未満 | 10kg~12kg | 12kg以上 |
| 特徴 | 持ち運びが非常に楽・階段も苦にならない | 持ち運びと走行安定性のバランス良い | 走行安定性高い・持ち運びに体力必要 |
| おすすめ用途 | 輪行がメイン・持ち運び頻度が高い | 普段使い+時々の持ち運び | ほとんど持ち運ばず安定性重視 |
安全基準「BAAマーク」を確認する
一つの安心材料として、「BAAマーク(自転車協会認証)」があります。これは、自転車協会が定めた約90項目もの厳しい安全基準をクリアした自転車にだけ貼付が認められるマークです。BAAマーク付きの製品は、少なくとも基本的な安全性は確保されていると考えて良いでしょう。
付属品の有無をチェックする
街乗りで使うなら、スタンドや泥除け、ライトは必須アイテムです。モデルによってはこれらが付属していない場合があるため、購入前に必ず確認しましょう。



後から取り付ける場合は、折りたたみの際に干渉しないかどうかも重要なチェックポイントです。
折りたたみ自転車のおすすめ人気商品


ここでは、信頼できるメーカーの中から、特におすすめの人気商品をいくつかご紹介します。それぞれの特徴を比較し、自分に合った一台を見つけてください。
【DAHON】 K3:驚異的な軽さと走行性能の両立
- タイヤサイズ: 14インチ
- 重量: 約7.8kg
10kgを大幅に下回る超軽量モデルでありながら、外装3段変速を搭載し、驚くほど軽快な走行性能を実現しています。コンパクトさと走行性能を高いレベルで両立させたい方におすすめです。輪行メインの方から絶大な支持を得ています。
【Tern】 Verge N8:スポーティな走りを実現する優等生
- タイヤサイズ: 20インチ (406)
- 重量: 約11.0kg
スポーティなデザインと高いフレーム剛性が魅力のモデルです。ロードバイクにも使われるコンポーネントを採用し、キビキビとした安定感のある走りを楽しめます。通勤から週末のサイクリングまで、幅広く対応できる万能さが人気です。
【HUMMER】 FDB206TANK-G:タフさが魅力のアウトドアスタイル
- タイヤサイズ: 20インチ
- 重量: 約17.2kg
その名の通り、戦車(TANK)のような頑丈なフレームと極太タイヤが特徴です。重量はありますが、その分、段差にも強く、非常に安定した乗り心地を提供します。アウトドアやキャンプシーンで映える、タフな一台を探している方におすすめです。
【RENAULT】 PLATINUM LIGHT 8 (AL167):エレガントなデザインの軽量モデル
- タイヤサイズ: 16インチ
- 重量: 約8.8kg
フランスの自動車メーカー、ルノーのブランドを冠したモデル。アルミフレームを採用し、16インチモデルでありながら9kgを切る軽さを実現しています。7段変速付きで走行性能も高く、デザイン性と実用性を兼ね備えています。



それぞれに個性が光る、おすすめの折りたたみ自転車です。
全国37の実店舗とオンラインストアで、国内サイクルブランドなら品揃えナンバーワンの「ワイズロードオンライン」こちらの記事「ワイズロードオンラインの評判って?口コミでわかる選ばれる理由とは」も、参考にしてください。
電動折りたたみ自転車で注目の商品


坂道の多い地域での利用や、体力に自信がない方、少し長めの距離を楽に移動したい方には、電動アシスト機能付きの折りたたみ自転車が非常に強力な選択肢となります。モーターのアシストにより、漕ぎ出しや坂道での負担が劇的に軽減されます。
電動折りたたみ自転車を選ぶポイント
1.バッテリー性能
走行可能距離と充電時間を確認しましょう。自分の用途に対して十分な容量があるかどうかが重要です。多くのモデルは30km~100km程度の走行が可能です。
2.重量
バッテリーとモーターユニットが加わるため、一般的な折りたたみ自転車より重くなります。15kg~20kg程度のモデルが多いですが、持ち運ぶ機会がある場合は、できるだけ軽量なモデルを選ぶのが賢明です。
3.アシスト性能
坂道でのパワフルさや、漕ぎ出しのスムーズさなど、アシストの特性もモデルによって異なります。
注目の電動モデル
1.【PELTECH】 TDN-208L
コストパフォーマンスに優れた人気のモデルです。20インチのタイヤと外装6段変速、十分な容量のバッテリーを搭載し、日常使いからサイクリングまで幅広く対応します。
2.【Holdon】 Q1J
14インチのコンパクトな車体で、デザイン性も高いモデルです。軽量で取り回しやすく、おしゃれに街を走りたい方におすすめです。
3.【TRANS MOBILLY】 E-MAGIC207
700Cの本格的なスポーツタイプの電動アシスト自転車で有名なTRANS MOBILLYの折りたたみモデルです。スポーティーな走行性能とアシスト機能を両立させており、長距離も快適にこなせます。



少しでも楽をしたいのであれば、価格は上がりますが電動折りたたみ自転車はおすすめです。
折りたたみ自転車に関するよくある質問
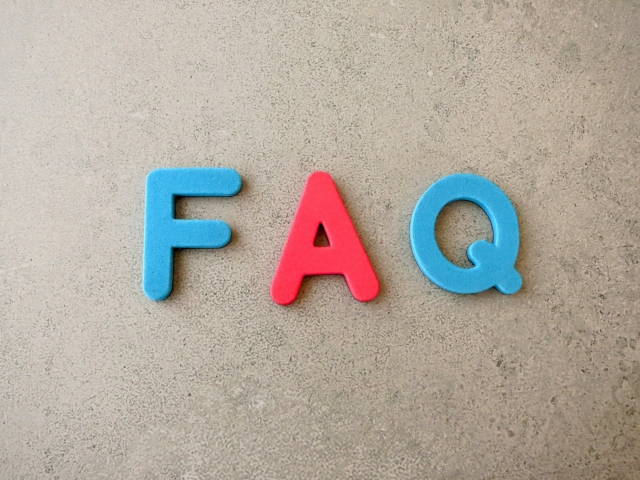
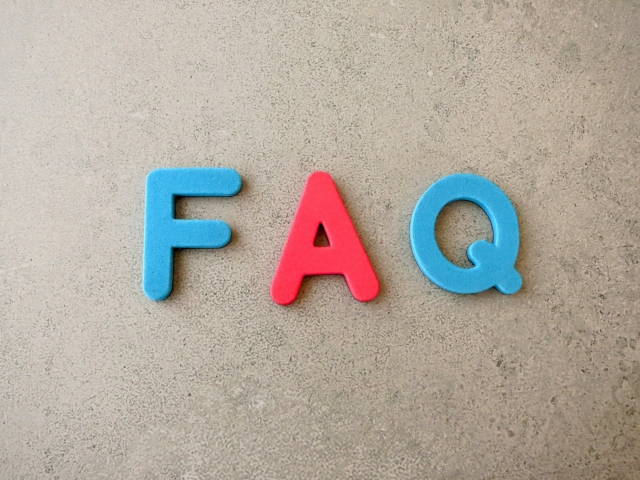
ここでは、折りたたみ自転車の購入を検討している方から寄せられる、よくある質問にお答えします。
- タイヤが小さいけど、たくさん漕がないと進まないの?
-
これは、半分正解で半分誤解です。タイヤが小さい(ホイール径が小さい)と、タイヤ一回転で進む距離は短くなります。しかし、多くの折りたたみ自転車では、この点を補うために「ギア比」が工夫されています。
ペダル側のギア(チェーンリング)を大きくすることで、ペダル一回転で後輪が何回転するかという数値を上げ、結果として小さなタイヤでも十分なスピードが出るように設計されています。そのため、品質の良いモデルであれば「たくさん漕がなければ進まない」ということはありません。
- 空気は抜けやすい?メンテナンスは大変?
-
タイヤが小さい分、空気の総量が少ないため、大きいタイヤに比べて空気圧の低下が早く感じられる傾向はあります。快適な走行を維持するため、1~2週間に一度は空気圧をチェックするのがおすすめです。
メンテナンスに関しては、折りたたみ機構がある分、可動部の点検や注油といった手間が少し増えます。しかし、基本的なチェーンの掃除や注油、ブレーキの確認などは一般的な自転車と変わりません。定期的なメンテナンスは、どんな自転車でも安全に乗るために不可欠です。
- メーカーによる違いは大きいの?
-
はい、メーカーによる違いは非常に大きいです。特に折りたたみ自転車は、フレームの設計や折りたたみ機構の精度が乗り心地と安全性に直結します。
DAHONやTernといった専門メーカーは、長年のノウハウを活かした信頼性の高い機構と、優れた走行性能を両立したモデルを多数開発しています。一方、無名の激安メーカー品は、安全基準を満たしていない可能性もあるため注意が必要です。



購入の際は、信頼できるメーカーの製品を選ぶことが、後悔しないための重要なポイントとなります。
【総括】買ってはいけない折りたたみ自転車とは
ここまで、折りたたみ自転車の様々な側面を解説してきました。最後に、この記事の要点をまとめます。これを踏まえれば、「買ってはいけない折りたたみ自転車」がどのようなものか、そしてあなたが選ぶべき一台がどのようなものかが明確になるはずです。
- 「買ってはいけない」と言われるのは、主に走行性能と価格の問題
- 速度が落ちやすく長距離では、疲れやすいのがデメリット
- 小径ホイールのため、走行安定性が低くふらつきやすい
- 折りたたみ機構は、異音や破損のリスクを抱える
- 同性能の一般車より、価格が高価になる傾向がある
- 特に10,000円台の激安品は、安全性に大きな懸念があるため避けるべき
- メリットは、圧倒的なコンパクトさと携帯性
- 室内保管できるため、盗難や劣化のリスクが低い
- 車や電車と組み合わせることで、行動範囲が広がる
- 街中でのストップアンドゴーが得意で、加速性能が高い
- 選ぶ際は用途に合ったタイヤサイズと、重量の見極めが肝心
- 通勤で使うなら、品質の良い変速付きモデルが必須
- ママチャリは実用性と積載性、折りたたみは収納性と携帯性で選ぶ
- DAHONやTernなど、信頼できる専門メーカーの製品を選ぶのが安心
- 坂道が多いなら電動アシスト付きが、非常に有効な選択肢となる








